
苗の出荷作業を行う立尾さん(左)とインドネシア人従業員。敷地内にある母屋の2階で暮らしている立尾さんは、農場のお父さん的存在です
ジャカルタ郊外の高原で、菊の苗がすくすくと育っています。沖縄県花卉(かき)園芸農業協同組合「太陽の花」(専門農協)が、沖縄名物の台風被害を避けるために、15年ほど前から始めた苗栽培の取り組みです。来年の正月や春のお彼岸に合わせ、航空便で日本へ順次配送。沖縄の菊農家が立派な花に育て、日本全国にある花屋の店頭に並びます。地元住民たちの雇用を生む菊の苗は、山村の活性化にも貢献しています。
ジャカルタから南へ車で3時間。郊外にある山村に入ると、菊の苗を育てるビニールハウスが並んでいます。標高910メートル。午前10時、気温は15度ほどでシャツ一枚では肌寒いほど。
広さ5ヘクタールの農場には、ネットハウスと雨よけハウスが57棟あり、毎年1200万―1600万本を沖縄に出荷しています。農場を管理する日本人は、社長の立尾肇さん(52)。ジャカルタの在留邦人からは「菊ちゃん」の愛称で呼ばれ、インドネシア滞在は通算5年目になります。
現地で多く家畜として飼われているやぎの糞を使って堆肥を作るなど、環境に合わせた栽培を模索してきました。乾季の水不足は、井戸水をくみ上げて問題を解消。苗の鮮度を保つために航空会社との調整に奔走し、現在は出荷から2日後の朝には沖縄に到着します。
■人柄に惚れ込んで
1972年に本土復帰する以前は、沖縄県産の農産物を県外輸出するには検疫や関税が必要で、出荷量は限られていました。しかし沖縄返還後は一転、沖縄の温暖な気候を生かした花卉栽培が全国的に注目を集めるようになります。
海外へ目を向けるきっかけとなったのは、春のお彼岸に向けた苗の採取時期が台風シーズンと重なり、しばしば甚大な被害を受けたことでした。1990年代にインドネシアでの現地生産をスタート。人件費の安さもあったが、現地調査に訪れた担当者らが村民たちの穏やかで誠実な人柄に接し、感動したことがインドネシア進出の決め手となったといいます。
■「従業員は家族さ」
同社は、繁忙期には約160人を雇用しており、地元の住民が現金収入を得る貴重な職場になっています。近隣の小学校に対しては、改築費の支援や文房具の寄贈を行ってきたほか、農業高校から研修生も受け入れている。パート労働者は、午前7時から午後3時まで農場での苗の植え付けや出荷作業を行います。月給は最低賃金に相当する約1万円ほど。
「なんくるないさ」の感性もそっくり。「のんびりと生活するインドネシアと沖縄の人々は本当によく似ています。インドネシア人従業員は私の家族です。彼ら、彼女たちの生活向上に貢献することも私の仕事です」。立尾さんは、うれしそうに語った。

整備が行き届いたハウス。設備のほとんどは現地で調達しました
レポーター「岡坂 泰寛」の最近の記事
「インドネシア」の他の記事
タグ:
- 2136 ビュー
- 0 コメント
![[International Messages Access]ima by kachimai 十勝から世界の今を伝えるサイト](../img/logo_page.gif)
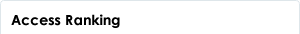
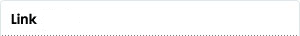



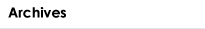
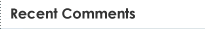


0 - Comments
Add your comments